車検でタイヤのひび割れについて不安を感じる方は、どこまでが車検通らない状態なのか、ディーラーでの判断や許容範囲を画像で確認する方法、側面とトレッド面で何が違うのか、さらにはひび割れがしやすいメーカーはあるのかといった点を知りたいはずです。
自分で点検したいユーザー車検派でも、検査の基準やバイクの扱い、ひび割れの進行レベルの見極めは迷いやすいテーマです。
本記事では基準の考え方と見分け方、現実的な対処法まで、初めての方にも理解しやすい形で整理します。
■本記事のポイント
- ひび割れの基準と車検で不適合となる代表例
- 側面とトレッド面の違いと見分けのコツ
- ディーラー/ユーザー車検別の実務的な対応
- バイクを含むレベル別の判断と交換タイミング
車検でタイヤのひび割れの基本知識
タイヤは車両の安全を支える最重要部品のひとつであり、車検では特に厳しくチェックされる項目です。
その中でも、ひび割れは見落としがちな劣化サインですが、放置すれば車検不合格や重大事故につながる恐れがあります。
実際に、国土交通省の基準では亀裂やコード露出があるタイヤは使用不可とされ、早期の点検と対応が不可欠です。
本章では、車検に通らないリスクと具体的な対策、ディーラーでの確認方法、業界団体が示すひび割れレベルの許容範囲、さらに側面とトレッド面それぞれに発生する特徴と注意点を詳しく解説します。
車検通らない場合のリスクと対策

タイヤのひび割れは単なる外観上の劣化にとどまらず、内部構造の安全性を損なう要因となります。
ゴムの表層に発生する微細なひびは進行するとコード層(繊維やスチールで補強された構造部分)にまで達し、最悪の場合は破裂や急激なエア漏れを引き起こす可能性があります。
特に高速道路走行中のバーストは重大事故に直結しやすく、社会的にも注意喚起が行われています。
国土交通省が定める道路運送車両の保安基準では、車検においてタイヤは「亀裂、損傷またはコードの露出がないこと」が明確に条件とされています(出典:国土交通省「道路運送車両の保安基準」)。
このため、ひび割れが深くコード層に達していると判断された場合は車検に通らない可能性が非常に高くなります。
また、車検不適合となったタイヤを使用し続けることは、操縦安定性の低下や制動距離の増加につながるとされています。
検査に備えて実践すべき対策は、まず定期的な目視点検を習慣化することです。
加えて、スリップサインの露出や空気圧不足といった別の不適合要因が同時に見られるケースもあるため、総合的な確認が不可欠です。
交換に際しては、4本同一メーカー・同一サイズに揃えることで車両挙動が安定し、整備記録としても一貫性が保ちやすくなります。
さらに、直射日光下での駐車や過荷重運転といった使用環境を見直すことが、再発防止につながります。
ディーラーでの確認と対応方法

ディーラーにおける点検は、一般的なガソリンスタンドやカー用品店と比較して、メーカー規定や技術基準に基づいた精密な診断が特徴です。
確認内容は主に以下の項目です。
●外観検査(ひび割れ、傷、膨らみの有無)
●残溝測定(デジタルゲージなどで精密に測定)
●空気圧点検(メーカー指定値との比較)
●偏摩耗の有無(アライメント不良の兆候も含む)
ひび割れの深さと位置(側面かトレッド面かを判別)
また、ディーラーではメーカー保証やリコール情報、サービスキャンペーンの適用可否を同時に確認してもらえる場合があります。
タイヤ交換時は単に溝やゴムの状態を見るだけでなく、荷重指数や速度記号、車種ごとの適合性を踏まえて推奨製品が提示されます。
見積もりを複数店舗で比較する場合は、作業工程に含まれる項目(例:バランス調整、バルブ交換、廃タイヤ処分費用)を明確に控えることが肝心です。
軽微なひび割れで交換か継続使用か判断が難しいケースでは、走行距離や次回点検までの期間を具体的に示した経過観察計画を立ててもらうことで、合理的な判断材料となります。
許容範囲 画像で確認できる目安
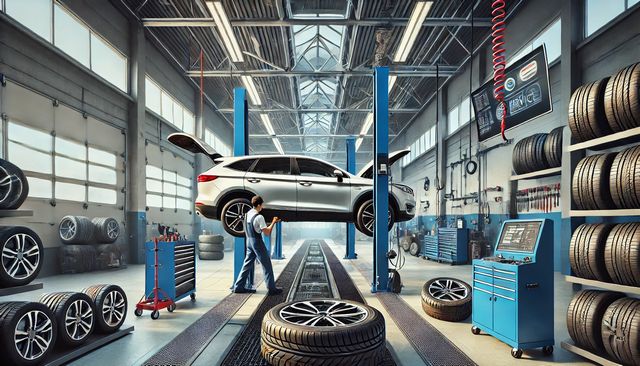
自己点検の参考資料として、日本自動車タイヤ協会(JATMA)は「クラック発生レベル」を画像で示し、レベル1から5までの目安を公表しています。
●レベル1から2:表面に浅い線状の割れがあるが継続使用可能
●レベル3から4:継続使用は可能だが定期的な経過観察が必要
●レベル5:コード層に到達している恐れがあり交換必須
このように段階的な基準を把握することで、ひび割れの深刻度を客観的に判断しやすくなります。
さらに、点検時には同じ角度や距離からタイヤを撮影し、月ごとに比較すると進行度を視覚的に確認できます。
ただし、画像判定は撮影条件や光の当たり方により見え方が変化するため、最終的な安全性の判断には限界があります。
特に、コード露出やひびの底が白く変色している場合は進行が疑われるため、直ちに使用を中止して専門家による確認を受けるべきです。
業界団体からも「コード露出が疑われる状態での走行は極めて危険」と注意喚起がなされており、安全性を最優先にした判断が推奨されます。
側面にひび割れが出たときの注意点

タイヤの側面(サイドウォール)は、走行中に大きくたわむ部分であり、車体の重量や路面からの衝撃を吸収する重要な役割を担っています。
そのため、側面に生じるひび割れはトレッド面よりも進行が速く、危険度が高い場合があります。
浅いクラックであっても繊維コード層に近接しているため、進行すれば破損に直結する可能性が高いのです。
側面にひび割れが発生する典型的な原因には以下のようなものがあります。
●空気圧不足や過荷重運転によるサイドウォールの過度なたわみ
●直射日光や紫外線によるゴムの劣化
●強い洗車用薬剤や油分がゴムに付着することによる化学的劣化
●縁石への接触や段差越え時の物理的ダメージ
点検時には、ひび割れの深さや長さ、本数に加え、指先で触れた際の段差感やひび割れの底の色合いも重要な観察ポイントとなります。
ひびの底が白っぽくなっている場合はゴム層が深く損傷している可能性があり、特に注意が必要です。
また、走行後や気温の変化によってひび割れの進行具合が変わることもあるため、定期的なチェックが欠かせません。
さらに、側面に膨らみ(バルジ)が生じている場合は内部コードの断裂が進んでいるサインであり、即座に使用を中止して交換することが強く推奨されます。
バルジを放置すると、わずかな衝撃でバーストに至る危険があるためです。
側面とトレッド面の比較表
| 部位 | 典型的な原因・誘因 | 進行の傾向 | 推奨対応の考え方 |
|---|---|---|---|
| 側面 | 空気圧不足、過荷重、薬剤、紫外線 | 進行が早い場合がある | 早期点検、深さや段差感があれば交換検討 |
| トレッド面 | 経年劣化、熱、走行距離 | 表面クラックは経過観察可も | 溝深さと併せて総合判定、コード到達は交換 |
この表からも分かるように、側面のひび割れはトレッド面より深刻度が高く、早めの交換判断が求められる傾向にあります。
トレッド面に発生するひび割れの特徴

トレッド面は路面との接触部であり、摩擦や熱の影響を強く受ける部分です。
ここに発生するひび割れは、ゴムの経年劣化や紫外線の影響で表面に細かい網目状のクラックとして現れることが多く、初期段階では深刻なリスクを伴わない場合もあります。
しかし、走行距離の増加や高温条件下での走行が続くと、トレッド面のひび割れは次第に深さを増し、溝底やブロックの付け根にまで達することがあります。
特に、亀裂が連続的に広がっている場合や、ひびの底がコード層に近づいている場合は交換が必要と判断されます。
日本自動車タイヤ協会(JATMA)が示す「クラック発生レベル」においても、トレッド面のクラックはレベル1から2であれば継続使用が可能とされていますが、レベル3以上になると経過観察から交換推奨へと移行します。
この基準は利用者にとって安全性を担保する重要な目安であり、単なる見た目だけでなく「深さ」「広がり方」「裂け目の一体化」といった要素を考慮した総合的な判断が欠かせません。
また、残溝が十分にあるからといって安心できるわけではありません。
ひび割れが進行すれば接地性能や排水性が損なわれ、雨天時のハイドロプレーニングのリスクが高まるためです。
定期的な残溝測定とあわせて、ひび割れの状態を観察することで、より精度の高い安全管理が可能になります。
トレッド面に関しては、走行後の熱が冷めたタイミングで点検するとひびの状態を正確に確認しやすくなります。
さらに、長期的な比較を行うために、定期的に同じ条件で写真を撮影して記録を残すことも有効です。
車検でタイヤのひび割れと対応方法の選び方
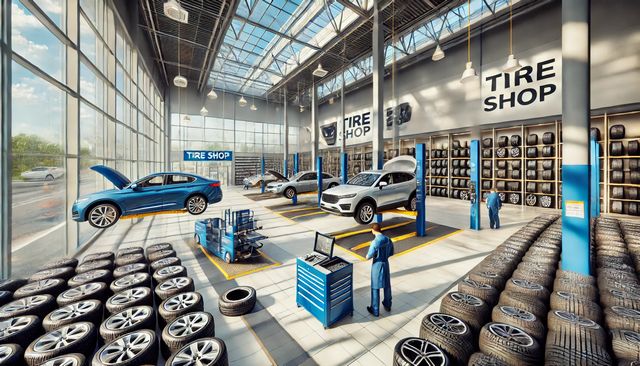
車検に備えるうえで、ひび割れへの対応は一律ではなく状況に応じた判断が求められます。
メーカーごとの設計思想による違いや、ひび割れの進行度を示すレベル判定、そしてユーザー車検ならではの注意点など、多角的に理解することで適切な選択が可能になります。
また、公的基準として何が確認されるのかを把握することは、余計なトラブルを避けるためにも欠かせません。
さらに四輪だけでなく二輪車も対象であり、バイク特有のリスクや交換の考え方も押さえておく必要があります。
ここからは、それぞれの観点を掘り下げ、実際にどう対応すべきかを具体的に解説します。
ひび割れしやすいメーカーの特徴

タイヤメーカーごとに設計思想や材料技術は異なります。
ゴムの配合成分、耐候剤や老化防止剤の種類、補強材の選定は、各社が研究開発で磨いてきた独自技術の反映です。
特に耐オゾン性と耐熱性の調整は、ひび割れの進行を左右する重要な要素となります。
オゾンは大気中に微量存在する気体で、ゴム分子を切断しやすい性質があり、耐オゾン性を高める添加剤の有無や量によって、タイヤ寿命に大きな差が生じるといわれています。
ただし、現時点で公的な比較試験において「特定メーカーの製品はひび割れしやすい」と断定できる公開データはほとんど存在していません。
タイヤの劣化はメーカー差以上に使用環境や管理状態に強く依存します。
具体的には以下の要素が大きな影響を与えます。
●車両重量や荷重配分
●空気圧の維持管理(過不足の放置)
●駐車環境(屋外での直射日光や雨風、屋内保管か否か)
●走行条件(高温・低温・未舗装路の割合)
●サイズ選定や荷重指数とのマッチング
このように、同じメーカーでも車両や利用条件によって耐久性は大きく変わるため、単にブランド名だけで判断することは適切ではありません。
特に屋外駐車が多い場合は、耐候性に配慮した製品設計やカーカバーの利用など、環境面での対策が効果的です。
結局のところ、メーカー選び以上に重要なのは、用途に合った規格の選定と日常的なメンテナンスであるといえます。
ひび割れの進行 レベルを見極める

タイヤのひび割れは進行段階によって対応方法が異なります。
日本自動車タイヤ協会(JATMA)は、クラックの進行度をレベル1から5に区分し、使用可否の判断基準を提示しています。
これは業界における標準的な目安として利用されており、特に整備士や車検検査員が判断を下す際の参考にもなっています。
| レベル | 状態の目安 | 推奨対応の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 表面に微細なシワや浅い線状 | 洗浄と保管見直し、通常使用で観察 |
| 2 | 目視でわかる浅い割れが点在 | 走行後に再確認、点検周期を短縮 |
| 3 | 連続性のある割れ、やや深い | 交換計画を立案、近い時期に更新 |
| 4 | 割れが広範・深い、段差感あり | 早期交換を推奨、長距離は避ける |
| 5 | コード層に到達・露出の疑い | 使用を中止し交換、プロ点検必須 |
特にレベル5に該当するコード層の露出は、車検に通らないだけでなく、走行を即刻中止すべき危険状態とされています。
業界団体も「コードに達した外傷や亀裂のあるタイヤは使用を控えるべき」と強調しており、安全の観点からも強制力のある注意喚起がなされています。
ひび割れは進行性があるため、目視確認を怠らず、段階的な評価と適切なタイミングでの交換を意識することが不可欠です。
ユーザー車検で注意すべきポイント

ユーザー車検は、自分で車検場に車を持ち込み検査を受ける制度で、整備士資格を持たない一般ユーザーでも利用可能です。
しかし、短時間で行われる検査の中でタイヤの状態は厳格にチェックされるため、事前準備が重要となります。
●検査ラインでは以下の項目が確認されます。
●外観に亀裂や膨らみがないか
●スリップサインが露出していないか
●タイヤサイズや表示が保安基準に適合しているか
●空気圧が適正値にあるか
事前点検では、タイヤを1本ずつ手やライトで確認し、溝深さゲージで残溝を測定することが推奨されます。
ひび割れが浅い場合でも、側面に連続性のある割れが広がっていると不適合となることがあるため、交換を視野に入れる判断が必要です。
また、異物が刺さっている状態や偏摩耗が見られる場合も検査官の指摘対象となります。
さらに、タイヤを交換した場合は取り付け後の空気圧調整、ホイールナットのトルク確認、走行100km後の増し締めを行うことで安全性が確保されます。
ユーザー車検に臨む際は、こうした一連の流れを自ら管理する責任が伴う点を理解しておくことが重要です。
車検の基準として見られるチェック項目

車検におけるタイヤ検査は、安全性を確保するために設けられた保安基準に基づいて行われます。
国土交通省が定める細目告示には、溝の深さ、ひび割れやコード露出、空気圧といった複数の観点が明示されており、いずれかが基準を満たさなければ不適合となります。
溝の深さは四輪で1.6mm以上、二輪で0.8mm以上が必要とされ、摩耗限度を示すスリップサインでの判定も認められています。
タイヤがこの基準に満たない場合は、制動距離が大幅に伸びたり、雨天時にハイドロプレーニング現象が起こるリスクが高まるため、走行自体が危険になります。
ひび割れやコード露出については、「著しい破損がないこと」が条件です。
側面やトレッド面に深い亀裂があり、内部の補強層が見え始めている場合は即座に交換が必要です。
特にコード露出は爆発的なタイヤ破裂につながるおそれがあるため、車検では最も厳格に扱われる部分です。
空気圧も重要なチェック項目です。
適正値を大きく下回っていると、車体の安定性低下や燃費悪化、タイヤの偏摩耗が進行しやすくなります。
逆に過充填もバーストの要因となるため、指定空気圧を正確に維持することが求められます。
| 項目 | 概要 | 出典の要点 |
|---|---|---|
| 溝の深さ | 四輪1.6mm以上、二輪0.8mm以上。
インジケータで判定可 |
保安基準細目 第89条(二から四) |
| ひび割れ | 亀裂・コード露出など著しい破損がないこと | 同上 第89条(三) |
| 空気圧 | 適正空気圧であること | 同上 第89条(四) |
このように、タイヤのひび割れだけでなく、残溝と空気圧も合わせて総合的に判断されます。
日常点検を怠らず、車検前だけでなく普段から基準を意識した管理を行うことが、検査をスムーズに通過する鍵となります。
バイクのタイヤひび割れと車検の関係

二輪車のタイヤは四輪車に比べて接地面積が圧倒的に小さく、その分ひとつのタイヤにかかる荷重が集中します。
このため、ひび割れが安全性に与える影響は大きく、操縦性や制動力に直結します。
保安基準では、二輪の溝深さは0.8mm以上とされています。
数値上は四輪より小さい基準値ですが、これはタイヤ構造や使用環境の違いによるものです。
ただし、ひび割れやコード露出の禁止条件は四輪と同じで、外観上の亀裂が深ければ即座に不適合となります。
特に二輪は側面の浅い割れでも進行が早い場合が多く、高速道路や炎天下での走行で一気に深刻化することがあります。
わずかな段差感や連続したクラックが見られた段階で交換を検討するのが望ましいとされています。
交換の際は前後同時に行うことが推奨されます。
前輪と後輪の摩耗状態が大きく異なると、直進安定性やコーナリング時の挙動に不均衡が生じるためです。
新品装着後は慣らし走行を経ることで、本来のグリップ性能が立ち上がり、より安全に使用することができます。
公的基準を満たしていても、二輪タイヤは実際の走行条件によって寿命が大きく変動するため、車検合格だけを目標にするのではなく、日常的な点検と早めの交換判断が安心につながります。
【まとめ】車検でタイヤのひび割れについて
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


