軽トラを13インチにカスタムしたいと考えている方にとって、「車検対応」は避けて通れないポイントです。
特に軽トラで13インチの車検対応の条件を満たすためには、タイヤやホイールのサイズ選びが非常に重要になります。
この記事では、「軽トラのタイヤは何インチまで履けますか?」という基本的な疑問から、スタッドレスやオフロードタイヤといった特殊用途への対応、6PRのような荷重規格への理解まで幅広く解説しています。
また、155/65R13 車検対応サイズの特徴や、軽トラ13インチタイヤホイールセット、さらには軽トラ13インチでマッドタイヤホイールセットの選び方についても詳しく紹介。
見た目や機能面でのメリットを享受しつつ、確実に車検を通すための知識を身につけたい方に最適な内容です。
■本記事のポイント
- 軽トラに13インチタイヤを装着する際の車検基準
- タイヤサイズや荷重指数の適合条件
- スタッドレスやオフロードタイヤの注意点
- 車検対応ホイールの選び方と必要なマーク
軽トラの13インチで車検対応のタイヤ選びポイント

軽トラを13インチ化する際、「車検対応」という言葉はとても重要です。
ただサイズが合うからといって、すべてのタイヤが問題なく使えるわけではありません。
タイヤの種類や規格、さらに装着後の見た目や安全性まで、多角的に確認が必要です。
ここでは、車検をスムーズに通すために欠かせない「6PR」や「荷重指数」などの基礎知識から、スタッドレスタイヤやオフロードタイヤといった特殊用途向けタイヤの注意点まで、わかりやすく解説します。
軽トラのタイヤは何インチまで履けますか?を解説

軽トラは純正で12インチまたは13インチタイヤが多いですが、14インチ以上でも車検を通すことは可能です。
ただし最大インチ数という明確な規定はありません。
重要なのは外径差が±3から5%以内に収まるタイヤを選ぶことです。
外径が大きくズレると速度計に誤差が生じ、車検に通らない場合があります。
ロードインデックス(耐荷重指数)は車検適合の大前提です。
軽トラにとって必要なのは、前後の軸重+最大積載量を踏まえたタイヤ1本あたりの最低耐荷重です。
荷重指数がこれを満たしていれば、たとえ乗用タイヤでも車検通過が可能です。
たとえば155/65R14でもLI75(約387kg耐荷)なら軽トラ向けとして認められる例もあります。
一方で、サイズ以外にも注意点があります。
ホイールのJWL-Tマークや、ホイール幅・オフセットが純正と極端に異なる場合はフェンダーとの干渉や見た目のはみ出しが問題になり得ます。
つまり、インチアップは自由ではなく、適切な外径差と耐荷重、干渉チェックがそろって初めて安全かつ合法的に可能になるわけです。
サイズ:155/65R13で車検通過の条件

155/65R13は軽トラのインチアップでよく選ばれるサイズですが、車検を通すためには以下の3つの条件を満たす必要があります。
まず、外径差が純正に対して±3から5%以内であることが望ましいです。
これはスピードメーターの誤差を防ぎ、検査時に許容範囲内とされるためです。
次に、ロードインデックス(LI)による耐荷重が、前後軸重+最大積載量を1本あたりで支えられる水準でなければなりません。
軽トラの場合、前軸が480kg、後軸が290kg、最大積載350kgとすると、実走行時には軸重合算で約730kgとなり、1本あたり最低でも365kg以上の耐荷重が必要です。
155/65R13のLIが73(約365kg)以上ならこの条件を満たします。
最後に、タイヤが車体外側にはみ出していないか確認が必要です。
整備士によっては見た目だけでNG判定されるケースもあり、特にフェンダーからの出具合やハンドル全切時の干渉チェックが重要です。
以上の条件をクリアすれば、155/65R13でも13インチ化として車検を無事通すことができます。
ただし実際の検査では検査員や車検場ごとの判断が入るので、事前確認や信頼できる整備工場での見積もりが推奨されます。
タイヤ:6PR規格や荷重指数にも注意

軽トラのタイヤ交換では、6PRなどのプライ(PR)規格だけで判断せず、荷重指数(LI)にも目を向ける必要があります。
6PRは商用車向けタイヤの一例で耐荷重約450kgを示しますが、軽トラには軽貨物車登録車としてこれに準じたタイヤが推奨されてきました。
ただし現在では、乗用車用タイヤでもLIが実際の軸重や積載重量を超えていれば車検に通る認識になっています。
この背景には法改正があります。
往々にして6PRやLT(ライトトラック)表示付きタイヤが“安全側”とされていましたが、今は荷重能力が基準を満たすかどうかが重要視されるようになりました。
こうしてLIの大切さが浮き彫りになったのです。
6PR相当であるLI80(450kg)なら、余裕を持って車検合格可能ですが、LI74~79(約365~425kg)程度でも、実際の軸重がそれ以下であれば合格例が多く報告されています。
一方で、元々が8PR標準の車両に6PRタイヤを履かせると規格ダウンと見なされ、車検不合格になる可能性があります。
したがって、適合するPR規格が標準であるか、LIがそれを上回っているかを必ず確認することが重要です。
結局のところ、軽トラのタイヤ選定では、実際の軸重+最大積載量を1本あたりで支えられる目安として、LIを重視すれば基本的に問題ありません。
ただし、安全マージンや車検時の判断を考えると、6PR相当(LI80)は安心感があると言えるでしょう。
スタッドレスやオフロードタイヤも車検対応可能?

軽トラに冬用スタッドレスタイヤやオフロードタイヤを装着する際も、車検は原則として通ります。
ただし、いくつかポイントがあります。
まず、スタッドレスタイヤでは、軽貨物用に設計された“バンタイヤ”規格が推奨されます。
商用車の耐荷重基準を満たしたものでなければ車検不合格になるケースもあります。
乗用車用スタッドレス(ブリザックREVO2など)ではLIが基準を満たす場合がありますが、“バンタイヤではない”という理由だけで見た目評価でNGとなる可能性もあるため、整備工場との事前確認が望ましいです。
オフロードタイヤに関しても、車検のポイントは「外径差」「荷重指数」「フェンダーからのはみ出し」「ホイール規格」。
外径が±4%以内で、LIと構造強度が適切であれば、ジオランダーなどのオフロードタイヤも合法です。
ただし、ロックギアやリム幅・オフセットが極端だと、車検時に干渉や不適合と見なされる恐れがあります。
また、オフロードタイヤを装着すると、舗装路でのロードノイズが増えたり、乗り心地が硬化したりというデメリットも生じます。
雪道や農道などが主用途であれば、高いグリップ性能や耐摩耗性が活きますが、日常的な街乗りでは過剰になることもあります。
つまり、スタッドレスやオフロードタイヤも車検は通りますが、荷重能力や外径適合を確保しつつ、見た目や干渉も整備工場と確認してから装着するのが賢明です。
軽トラの13インチで車検対応のホイール&セット購入ガイド
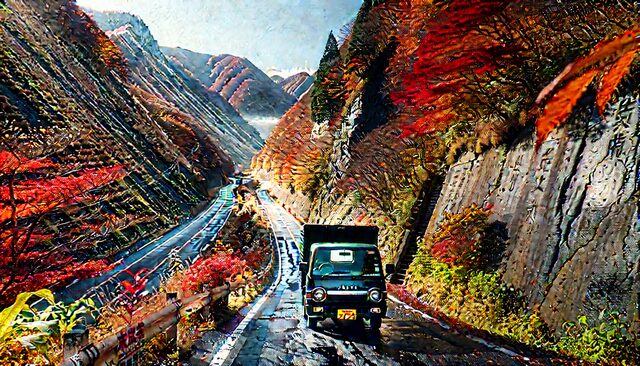
軽トラを13インチにカスタムする際、タイヤと同じくらい重要なのが「ホイール選び」です。
特に車検に対応したセットを選ぶには、安全性や法的基準を正しく理解することが欠かせません。
JWL-Tマークの有無やホイールサイズの適合性によって、車検で不合格になるケースもあります。
また、13インチ化によってどんなメリットがあるのか、逆にどんな点に注意すべきかも知っておきたいところです。
ここでは、購入前に知っておくべき重要ポイントを詳しく解説していきます。
13インチタイヤホイールセットの選び方

軽トラに13インチタイヤとホイールのセットを選ぶ際は、まず「ミニマムな法的要件」を抑えることが重要です。
具体的には、タイヤサイズが外径差±3から5%以内かつ荷重指数(LI)が軸重+積載量をカバーできることを確認します。
また、ホイールにはJWL-Tマーク付きの商用車用アルミが求められるケースが多く、安全性と耐久性の目安になります。
一方で、扱いやすさや見た目の好みとして、ブラックスチールホイールにブロックパターンを組み合わせたセットが人気です。
155/65R13+13×4.0Jのような組み合わせは外径差が小さく、車検リスクも低い上、アウトドアや作業車風のルックスが手に入り、初心者にもおすすめです。
さらに、購入するときは価格帯とブランド、バランス調整や工賃も含む総額を見積もりましょう。
楽天市場やYahoo!ショッピングでは4本セットで3から7万円台が相場で、レビューや評価をしっかりチェックすれば、納得のいく選択ができます。
マッドタイヤホイールセットの特徴

軽トラに13インチのマッドテレーン(M/T)タイヤとホイールを組むと、未舗装路や悪路での走行性能が大きく向上します。
マッドスターなどの製品は155/65R13や165/70R13が主流で、深いトレッドブロックが泥や砂利をしっかりグリップし、農作業やキャンプで好まれる仕様です。
このセットは見た目にインパクトがありますが、舗装路ではロードノイズが大きく、乗り心地が硬い点がデメリットとなります。
また、外径差やオフセットによっては車体とのクリアランスに余裕が必要で、念のため事前に整備工場で確認しておくことが安心です。
とはいえ、河原や山林などオフロード中心の用途であれば、強い走破性と個性的なルックスを得られる点で、軽トラの使い方に合わせた賢いカスタムと言えるでしょう。
価格は4本セットで3から4万円台からあるので、導入しやすい点も魅力です。
軽トラ用ホイールにJWL-Tマークが必要な理由

軽トラは貨物車として登録されるため、ホイールには「JWL-T」もしくは「JWL」マークが必要です。
これは国土交通省が定めた基準を満たしている証で、安全性や耐荷重性能を確保していることを示します。
特にJWL-Tはトラックやバス向けに高い耐久性が求められ、装着してないホイールでは車検が通らないのが原則です。
ただし2014年に軽トラでも乗用車向けのJWLマークのあるホイールが適合とされるようになりました。
それでも整備士によってはJWL-T刻印を重視し、検査で不合格になるケースがあるので注意が必要です。
さらに第三者認証の「VIAマーク」があれば、より信頼性が高く安心感があります。
そのため、軽トラの13インチ化でアルミホイールを選ぶ際は、まずJWL-TまたはJWL刻印付き、できればVIA登録済みの製品を選ぶのが安心です。
これを満たせば車検対応のホイールとして問題なく装着できます。
メリット:13インチ化による利点とデメリット比較

軽トラを13インチにインチアップすると、見た目や性能面でいくつかの利点が得られますが、一方でデメリットや注意点も存在します。
まずメリットとして、見た目のドレスアップ効果が高くなります。
ブラック系ホイールで足回りが引き締まり、作業車の印象がグッとワイルドになります。
また、接地面が広がるためグリップ力とブレーキ効率も向上し、コーナリングで安定感が増すのも特徴です。
さらに外径がわずかに増えることでメーターの誤差を補い、結果として燃費や静粛性が良くなったという声もありますが、これはサイズと組み合わせ次第です。
一方でデメリットも明確です。
サイドウォールが薄くなることで舗装路では乗り心地が固く感じやすく、路面の振動や衝撃が車内に伝わりやすくなります。
さらに転がり抵抗の増加により燃費が悪化する可能性もあり、ロードノイズが気になるケースもあります。
また極端に大きなサイズやオフセット不適合を選択すると、フェンダー干渉やスピードメーター誤差で車検が不安定になるリスクがあります。
このように、13インチ化はデザイン・走行性能向上の魅力があるものの、乗り心地・燃費・車検リスクなども総合して判断することが大切です。
購入前には整備工場に相談し、外径差やオフセットを確認したうえで装着することをおすすめします。
【まとめ】軽トラで13インチの車検対応について
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


