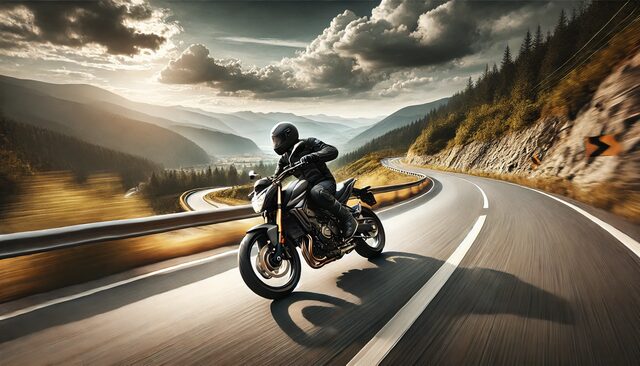400ccバイクで車検が廃止と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、制度の変更時期や実際の費用、手続きの流れについて具体的に知りたいのではないでしょうか。
400ccのバイクの車検の平均価格は?
車検が廃止されたら費用はいくらになる?
いつから変わるのか?
といった疑問のほか、陸運局での手続きが必要かどうか、自分で対応する場合の注意点、レッドバロン費用との比較なども気になるポイントだと思います。
また、一時抹消手続きやカスタムの合法性、中型バイクに車庫証明は必要ですか?
という関連テーマについても正確な理解が求められます。
本記事では、そうした疑問を一つひとつ解消しながら、現在の制度の正しい理解と今後への備えをわかりやすく解説します。
■本記事のポイント
- 車検廃止の噂がいつから出たのか
- 400ccバイクの車検費用の相場
- 陸運局での手続きやその継続可能性
- 一時抹消やカスタムに関する法的注意点
400ccバイクの車検廃止は現時点で実現するのか

現在、250cc以下のバイクは車検が不要である一方、400ccクラスは継続的に車検を受ける義務があります。
そのため、多くのライダーが「400ccバイクの車検も廃止されるのでは?」と関心を寄せています。
しかし、制度はそう簡単に変わるものではありません。
ここでは、車検廃止の話がいつから出ているのか、そして制度変更によって陸運局での手続きは本当に不要になるのかなど、制度の動向や実務上の影響について詳しく解説していきます。
いつから車検廃止の話が浮上したか

2010年代後半から、「250cc以下は車検不要で、400ccも同様になるのでは」という噂がライダーの間で出始めました。
特に250cc以下のバイクが車検対象外であることと比較され、「400cc車検廃止」への期待が高まりました。
前述の通り、2023年の時点では正式な車検廃止の決定は一切ありませんでした。
国交省や関係官庁から正式発表もなく、制度そのものは維持され続けています。
ただ、噂が出た背景には、250cc以下の車検不要制度と比較されることや、維持費軽減の動きも知られています。
法令の根拠である道路運送車両法と自動車重量税の税収確保の観点から、制度変更には慎重な姿勢が見られるのが現実です。
現時点でも、車検制度を廃止する具体的な動きや法改正の動きは確認されておらず、2025年7月時点では車検義務は引き続き適用されています。
制度変更の報道や公式発表があれば、新たに注目すべき情報として扱う必要があります。
400ccのバイクの車検の平均価格は?費用いくらか
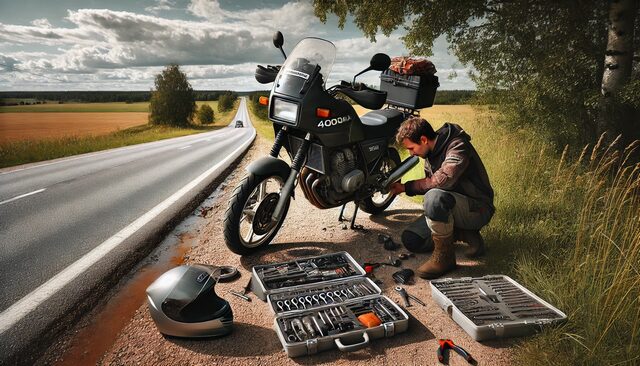
トータルの車検費用は、法定費用と基本料に分かれます。
法定費用は、自動車重量税・自賠責保険・印紙代の合計であり、これはどの方法でも支払う必要がある固定費です。
たとえば13年未満の車両では重量税が3,800円、自賠責が約9,700から9,800円、印紙代が1,300から1,750円で、合計約1万5千円から1万9千円となります。
一方、業者に依頼した場合の基本料金は、代行店やディーラー、認証工場などによって異なります。
一般的には、代行業者で約3万から4万円、ディーラーでは4万から6万円、店舗や整備内容によっては6万円以上になるケースもあります。
ユーザー車検を選ぶ場合は、基本的に法定費用のみで済むため、合計で約2万円前後に抑えられます。
ただし、整備・点検を自分で行う手間や知識が必要で、不合格時には再検査のための追加費用や時間がかかる点に注意が必要です。
このため、多くの人は手間を避けつつ信頼性も重視して、代行業者やディーラーへの依頼を選ぶ傾向にあります。
費用相場としては、トータルで2万から6万円程度と覚えておくと良いでしょう。
以上、初めての読者でも理解しやすいように車検の発生時期や背景、費用内訳とその目安を整理しました。
陸運局手続きをなくせるかどうか
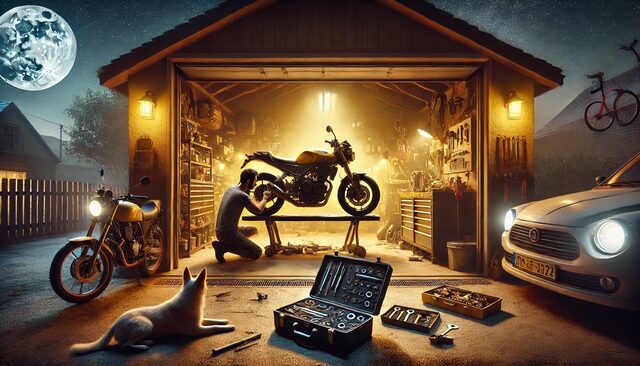
現在では、400ccクラスのバイクを廃車にする際には必ず陸運局(運輸支局や自動車検査登録事務所)での手続きが必要です。
必要書類には車検証、ナンバープレート、軽自動車税申告書、抹消登録申請書(第3号様式の2)、手数料納付書、印鑑などが含まれ、窓口で書類の作成やナンバープレート返納の手続きもあります。
いくら制度が変更されても、バイクの登録情報を公式に抹消する手続きは国交省が所管しており、インフラのデジタル化が進んだとしても、舟車の渡し替え的な行政処理なしに完全に省略されるのは現実的ではありません。
たとえば他国の例を見ても、登録・税制度と車検制度は行政上密接に絡んでおり、車検廃止だけで役所手続きをなくすというのは難しい見通しです。
もし仮に車検制度自体が撤廃されたとしても、ナンバープレート返納や税務上の申告などは残る可能性が高く、陸運局での書類提出や印紙購入などの手間は継続されるでしょう。
そのため、制度変更によって完全に陸運局手続きをなくせるという期待は持たないほうがよいと考えられます。
一時抹消登録との関係性

まず、一時抹消登録とは、使用を一時的にやめるために車両登録情報を一時的に抹消する手続きです。
たとえば長期出張や入院、しばらく乗らない場合に適しています。
この手続きを行うことで軽自動車税の課税停止、自賠責保険や任意保険の等級維持などのメリットがあります。
一方で、400ccなど車検対象のバイクを再び走らせる場合には、再登録の際に必ず車検を通す必要があります。
予備検査証の有無にかかわらず、再使用時には運輸支局に持ち込んで検査ラインを通す手間と費用が発生します。
「バイク 400cc 車検 廃止」がもし実現したとしても、一時抹消制度の存在自体は別個の制度であるため、抹消したバイクを再登録する際の形式や抹消手続きの仕組みが変わる可能性は低いです。
むしろ、車検義務がなくなった後でも税や登録の制度は残るでしょうから、一時抹消申請や再登録の際の書類・印紙・ナンバープレート返納の流れは維持されると考えられます。
したがって、「車検廃止=一時抹消も不要になる」という誤解は避けたほうがよく、両制度は独立して理解し、必要に応じて適切な手続きをとることが重要です。
400ccバイクの車検廃止になったらどう変わるか

もし400ccバイクの車検が廃止されたとしたら、私たちのバイクライフはどのように変わるのでしょうか。
費用負担が軽くなるだけでなく、整備やカスタムの自由度、そして手続き面にも大きな影響があるかもしれません。
ここでは、ユーザーが自分で対応する必要があるのか、カスタムの自由度はどこまで広がるのか、さらには中型バイクに関する車庫証明の必要性まで、制度が変わった場合に想定される実際の変化を詳しく見ていきます。
自分で車検対応する必要は?

現在の制度では、継続検査を「ユーザー車検」で自分で受ける方法もあります。
この方法なら法定費用(自賠責保険・重量税・印紙代)だけで済むため、費用を大幅に抑えられます。
例えば重量税3,800円、自賠責(24ヶ月)約8,760円、印紙代約1,700円で合計14,000円台からが相場です。
ただし、自分で手続きと整備を行う必要があり、書類記入、予約、点検、現地持ち込みなどの手間がかかります。
不具合があると再検査や整備に時間や追加費用が発生するため、バイク知識や道具も必要です。
このため、「車検廃止」がもし実現したとしても、陸運局への書類提出や整備の自力対応は維持される可能性が高く、手続き自体が不要になるわけではありません。
自分で対応する負担は完全には消えないと考えたほうがよいでしょう。
レッドバロンでの車検費用との比較

レッドバロンで400cc車の車検を受けると、基本料金12,010円に加え法定費用(自賠責約8,900円、重量税5,000円、印紙代1,700円)と代行手数料21,000円がかかり、合計は約48,000円程度が最低ラインとなります。
ただ、実際には点検や部品交換が必要になるケースが多く、多くの利用者は5から7万円、場合によっては10万円以上になることもあります。
一方でユーザー車検だと、法定費用のみで済む場合、2万円前後(14,000から20,000円)が相場となります。
レッドバロンはプロによる84項目超の整備やフレーム検査などの安心感があり、整備品質や手間削減を重視する方には適しています。
これに対して、自分で費用を節約しつつ整備に自信がある方ならユーザー車検が適しています。
このように、費用と対応の手間、安全性のどれを重視するかで適切な選択が異なります。
カスタムへの影響と合法性

もし制度が変わって車検義務がなくなっても、構造変更が必要なような大幅な改造には法的な規制が残ります。
たとえば車高を25mm以上変えたり、サイズ外のタイヤ・ホイールを装着したりする場合は、構造変更申請が必要であり、これを怠ると違法運転となる可能性があります。
あるいはシートをタンデム不可のタイプに交換した場合、乗車定員の変更申請を出さずに走ると、整備不良として違反になるリスクもあります。
だからこそ、カスタムを楽しむにあたり重要なのは、パーツが車検基準に適合しているか、また必要に応じて構造変更申請を提出しているかを確認することです。
専門ショップでの相談や、適合証明のあるパーツ使用が安全です。
つまり、車検がなくなっても「自由に改造できる」という誤解は避けるべきで、法令に基づく手続きを踏まえながら、合法範囲内で安心してカスタムを楽しむことが大切です。
中型バイクに車庫証明は必要ですか?

バイク全般については「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の対象外とされているため、原付も250cc超も400ccクラスも、いずれも車庫証明の提出義務はありません。
具体的には、251cc以上の中型バイクであっても、自治体に対して駐車場所の証明を行う必要はないのです。
ただし、駐車場契約時に貸主から「保管場所使用承諾書」の提出を求められるケースもありますが、あくまで契約上の取り決めであり、法的な車庫証明とは異なります。
一方で、違法駐車や路上に無断で放置すれば、道路交通法違反となり罰則を受けるため、適切な駐車場所の確保はもちろん重要です。
したがって、中型バイクだからといって車庫証明が必要になるわけではなく、安全性とルールを守りつつ、安心してバイクライフを楽しむために、駐車場所の確認や選び方に注意しておくことが大切です。
【まとめ】バイクで400ccの車検が廃止について
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。