車検どれくらいかかるのかは、費用も時間も条件で大きく変わります。
軽自動車と中古車では内訳が異なり、バイクは排気量で必要かどうかが変わります。
トヨタやホンダ、日産、マツダ、ダイハツ、スズキといったメーカー別の目安や、オートバックスやコバックの短時間メニュー、陸運局に直接持ち込む方法まで、見積もりの取り方を含めてわかりやすく整理します。
迷いどころを一つずつ解消し、最適な受け方を選べるようにご案内します。
■本記事のポイント
- 車検費用の内訳と相場の考え方
- 車検時間の目安と早く終えるコツ
- 店舗別やメーカー別の選び方の違い
- 見積もりと予約で失敗しない手順
車検どれくらいかかるかの基本ポイント
車検は安全に車を走らせるために欠かせない制度ですが、いざ受けるとなると「どれくらい費用がかかるのか」「時間はどの程度必要なのか」といった疑問が多く寄せられます。
実際のところ、車検費用は法定費用と整備費用で構成され、整備内容や受ける場所によって総額は大きく変わります。
また、ディーラーや専門店、ユーザー車検といった選び方で所要時間にも違いが生まれます。
さらに、軽自動車やバイク、中古車といった車種ごとの特徴、見積もりの取り方、陸運局での流れを知っておくことで、余計な出費や手間を避けられます。
ここからは、それぞれのポイントを順に詳しく解説していきましょう。
車検の費用はどう決まるのか

自動車の車検にかかる費用は、大きく分けて「法定費用」と「サービス費用」の二つの要素から構成されます。
法定費用は国に支払う必須の金額であり、車種や経過年数に応じて変動します。
一方、サービス費用は整備工場やディーラー、カー用品店などが独自に設定する料金であり、店舗の方針や整備内容によって差が出ます。
読者が疑問を感じやすいポイントとして「なぜ同じ車でも店舗によって金額が違うのか」が挙げられますが、まさにこのサービス費用が影響しているのです。
法定費用に含まれるのは、自賠責保険料、重量税、そして検査登録にかかる手数料です。
例えば、2025年度時点で自家用普通乗用車の自賠責保険料(24か月契約)は17,650円とされています。
軽自動車の場合は24か月で17,540円とわずかに安く設定されています(出典:国土交通省 自動車局 自動車技術安全部)。
これらは年度ごとに見直しが行われるため、車検を受ける直前に最新の金額を確認することが不可欠です。
サービス費用の内訳は多岐にわたり、基本的な24か月点検、完成検査、書類作成にかかる「基本料」、検査ラインへの持ち込みや書類申請を代行してもらうための「代行料」、そしてブレーキパッドやエンジンオイル、バッテリーといった消耗部品の交換にかかる「部品・整備費用」が代表例です。
店舗によっては、早期予約割引、平日限定の特別料金、リピーター向けのメンテナンスパックなどを用意しており、これらを活用すると総額が数千円から数万円単位で抑えられることがあります。
相見積もりを取る際は、単純に総額だけを見るのではなく、同じ部品のグレード(純正・社外・リビルトなど)や工賃の範囲を統一して比較することが大切です。
同じ車検整備でも、部品の選び方一つで耐用年数や性能に大きな差が生まれるため、価格と品質のバランスを理解したうえで選択することが安心につながります。
| 区分 | 代表的な中身 | 価格変動の主因 |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料・重量税・検査手数料 | 車種・経年・年度改定 |
| 基本料 | 24か月点検・完成検査・書類 | 店舗ごとの設定 |
| 代行料 | 申請・回送・印紙手続き | 受け方や地域差 |
| 部品・整備 | ブレーキ、油脂類、消耗品 | 劣化状況・希望整備 |
車検にかかる時間の目安を知る

車検に必要な時間は、どこで受けるか、そしてどの程度の整備を行うかによって大きく異なります。
ディーラーや認証整備工場であれば、点検から整備、試運転までを丁寧に行うため、半日から2日程度かかるのが一般的です。
一方で、カー用品店や車検専門店の中には、最短60分から対応可能とアピールしているところもあります。
ただし、受付や会計、整備内容の説明を含めると、実際には半日程度を見込む必要があります。
また、短時間で終わるコースは、あくまで消耗部品の交換がほとんど不要な場合に限られます。
走行距離が多い車や年式の古い車では、追加整備が必要になり、結局は数時間から1日程度かかるケースが多く見られます。
ユーザー車検の場合は、陸運局や軽自動車検査協会での検査ライン通過に加え、書類作成や並び時間を考慮すると、全体で半日から1日を要することが多いです。
| 受け方 | 目安時間 | 向いている人の例 |
|---|---|---|
| ディーラー・整備工場 | 半日から2日 | 保証・点検記録を重視 |
| カー用品店 | 最短60分から半日 | 当日返し重視・立会い希望 |
| 車検専門店 | 45分から1日 | 速さ重視・標準整備中心 |
| ユーザー車検 | 半日から1日 | 自分で段取りできる人 |
計画を立てる際は、点検・整備そのものの時間に加えて、受付や待合室での待ち時間、見積もりや説明にかかる時間も含めて逆算することが求められます。
また、代車が必要かどうか、土日祝日の対応可否、予約の取りやすさなども含めて検討することで、スケジュールに無理のない車検を受けられるようになります。
軽自動車の車検費用と特徴

軽自動車は、普通車に比べて法定費用が低く抑えられているため、総額も安く済むことが多いのが特徴です。
2025年度の自賠責保険料(24か月契約)は17,540円とされており、普通車よりもやや安価です。
重量税はエコカー減税の適用状況や経過年数によって変動します。
例えば、新しいエコカーであれば重量税が軽減される一方、13年以上経過した車両では重量税が上がる仕組みになっています(出典:国土交通省 自動車重量税制度)。
ただし、軽自動車であっても走行距離が長い場合や、タイヤ・ブレーキ・バッテリーといった消耗品が劣化していれば追加費用は避けられません。
特に軽自動車は車体が軽いためブレーキにかかる負荷が小さいという利点がありますが、その分エンジン回りや電装品が酷使されやすく、交換が必要になるケースもあります。
こうした点を踏まえ、事前に点検を受けて消耗品の状態を確認しておけば、見積もり時の想定外の出費を減らすことができます。
さらに、軽自動車は維持費の安さから普及台数が多く、ディーラーや整備工場における部品供給体制が整っています。
このため、修理や交換の対応がスムーズであるという利点もあります。
代車の有無、土日の対応可否なども確認し、ライフスタイルに合った店舗を選ぶと効率よく車検を進められるでしょう。
バイクの車検に必要な条件

二輪車における車検の要否は、排気量によって大きく異なります。
排気量が250ccを超えるバイクは車検の対象となり、新車登録から3年後が初回車検、その後は2年ごとに継続車検を受ける必要があります。
これは道路運送車両法で定められている基準であり、違反すると公道を走行できなくなるため、必ず守らなければなりません。
一方、250cc以下のバイクについては車検は不要ですが、安全確保の観点から定期点検や日常整備は欠かせません。
車検に必要な書類としては、自動車検査証(車検証)、自賠責保険証明書、重量税納付書、継続検査申請書、納税証明書などが挙げられます。
さらに、陸運局や軽自動車検査協会に提出するための検査票も必要になります。
費用は自賠責保険料(24か月で約9,270円から)、重量税(排気量や経過年数によるが、通常は5,000から10,000円程度)、検査手数料に加え、整備費用や代行料がかかります(出典:国土交通省「自動車検査制度」)。
また、バイク特有の注意点として、マフラーやハンドルなどカスタム部品を取り付けている場合があります。
保安基準に適合していない部品を装着したままでは検査に通らないため、事前に基準適合品かどうかを確認し、必要に応じて純正部品に戻す準備を進めておく必要があります。
安全装備の不備やタイヤ摩耗も不合格の要因になるため、点検を怠らないことが合格の近道です。
中古車の車検で注意すべき点

中古車を購入した場合、車検においては新車と異なる注意点があります。
まず、前オーナーの整備履歴がどこまで残っているかが重要です。
正規ディーラーでの整備記録簿があれば、過去にどのような整備や交換が行われてきたかが明確であり、車検時に必要な追加整備を予測しやすくなります。
しかし、履歴が不十分な中古車では、部品の劣化や不具合が発見され、想定外の費用が発生するリスクが高まります。
特に注意すべきなのは、社外品パーツや改造部品が取り付けられている場合です。
ヘッドライトの光度不足や排気音量の超過などは保安基準不適合の典型例であり、車検不合格の原因になります。
こうした場合には純正部品への交換や調整が必要で、その費用も見積もりに含まれることになります。
さらに、中古車の購入時期と車検時期が近い場合は、名義変更と車検の両方を行わなければならないケースもあります。
特に車検切れの状態で購入した場合には、仮ナンバーを取得して車検場まで回送するなど、通常とは異なる手続きが必要になります。
販売店がどこまでサポートしてくれるのかを事前に確認しておくことが安心につながります。
また、保証継承を希望する場合には、メーカーの正規ディーラーで車検を受ける必要があるケースもあります。
保証継承とは、前オーナーが加入していたメーカー保証を次の所有者に引き継ぐ制度であり、これを受けるにはディーラーで所定の点検を受けることが条件となります。
中古車であっても保証を活用したい場合は、車検をどこで受けるかの判断材料となります。
車検の見積もりを取る際の流れ

車検を受けるにあたって最初のステップとなるのが見積もりです。
見積もりは最低でも2から3社から取得し、比較することが推奨されます。
ここで注意すべきは、単純に総額だけを比較するのではなく、法定費用と整備費用の内訳を細かく確認することです。
法定費用はどの業者でもほぼ同一ですが、整備費用や代行料は大きく異なります。
見積もりを依頼する際には、希望する整備内容の優先順位を明確にしておくとスムーズです。
例えば「安全性を最優先にする」「快適性も重視する」といった基準を示すことで、業者も適切な整備プランを提案しやすくなります。
部品については純正品、優良部品(社外品)、リビルト品の選択肢があります。
それぞれ価格や耐用年数、保証内容が異なるため、見積もりの際には同条件で比較することが重要です。
さらに、見積書には追加整備の条件や、発生時の連絡方法、納車予定日なども明記されているかを確認しましょう。
特に、ブレーキやタイヤの劣化など安全に直結する部品は車検当日に不合格とされる可能性が高いため、追加整備費用が発生することを前提に予算を立てておくと安心です。
見積もりで確認したいポイント
・法定費用と整備費用の内訳
・追加整備の判断基準と連絡方法
・代車、送迎、引き取りの可否
・クーポンや早割、決済条件の適用範囲
これらを明確にすることで、予想外の出費や納期遅延といったトラブルを防ぐことができます。
信頼できる業者を選ぶためには、価格の安さだけではなく、説明の丁寧さやアフターフォローの有無も重要な判断基準となります。
陸運局で受ける車検の手順

陸運局や軽自動車検査協会で行う「ユーザー車検」は、費用を抑えられる方法として知られています。
専門業者に依頼する場合と比べると、代行料が不要なため総額を大幅に安くできる可能性がありますが、必要な手続きや流れを自分で理解して実行する必要があるため、ある程度の知識と準備が求められます。
ユーザー車検を受けるには、まず自動車検査インターネット予約システムで日時を予約する必要があります。
予約は通常、受検日の約2週間前から受付が可能で、土日祝日や年末年始は受付が行われません(出典:自動車技術総合機構「自動車検査インターネット予約システム」)。
予約番号は当日の受付時に必要となるため、控えておきましょう。
必要書類は以下のとおりです。
・自動車検査証(車検証)
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
・自動車税納税証明書
・継続検査申請書
・重量税納付書
・検査手数料を支払うための印紙・証紙
これらの書類は事前に準備しておき、当日は受付窓口で提出します。
なお、様式は運輸支局や軽自動車検査協会の窓口、または公式サイトから入手できます。
検査当日の流れとしては、受付後に書類審査を受け、その後に検査ラインへ進みます。
検査ラインでは、外観検査、ライトやウィンカーなどの灯火類、ブレーキやスピードメーター、排気ガスの測定などが行われます。
最後に下回り検査を通過すれば合格となり、新しい車検証とステッカーが交付されます。
不適合が見つかった場合は、整備を行った後に再度検査を受けることが可能です。
普通車は国土交通省管轄の運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口となります。
この違いを理解しておかないと、誤った窓口に出向いて時間を無駄にしてしまうため、必ず事前に確認しておきましょう。
ユーザー車検は費用を抑える魅力がある一方で、検査ラインでの操作や手続きに不慣れだと戸惑う場面が多くあります。
そのため、初めて挑戦する場合には、あらかじめ公式マニュアルや手順書を確認して流れを把握しておくと安心です。
また、法定点検を省略して良いわけではないため、検査を通した後も定期的なメンテナンスを怠らないことが安全運転につながります。
車検どれくらいかかるかをメーカー別に解説

車検費用やかかる時間は、同じ車でもメーカーや車種によって傾向が異なります。
たとえば、トヨタのように部品流通が豊富なメーカーは比較的選択肢が多く、ホンダは駆動系の特性から所要時間に影響が出る場合があります。
日産は電動化技術が進んでおり、特有の点検が費用に反映されます。
さらに、マツダやダイハツ、スズキといったメーカーは車種の特徴や使用環境によって注意点が異なります。
加えて、オートバックスやコバックといった専門店での受け方を知ることで、効率的に車検を進めるヒントが得られるでしょう。
トヨタ車の車検費用と傾向

トヨタは国内最大級のシェアを誇り、軽自動車から高級セダン、SUV、商用車まで幅広い車種を展開しています。
そのため、車検費用にも一定の傾向があります。
最大の特徴は、部品の流通量が非常に多く、純正部品だけでなく社外品やリビルト部品の選択肢が豊富にある点です。
これにより、ユーザーは価格と品質のバランスを取りながら整備を進めやすい環境が整っています。
さらに、トヨタは全国の販売網が広いため、ディーラーでの車検を選ぶとメーカー保証やメンテナンスパックが適用される場合があります。
特にメンテナンスパックに加入している場合、オイル交換や消耗品交換の一部が事前に支払い済みとなっており、車検時の追加費用が軽減されるケースがあります。
延長保証プランを利用している場合も、故障リスクを抑えた状態で車検を受けられるメリットがあります。
また、トヨタはハイブリッド車の普及率が高いメーカーであり、補機バッテリーやインバーター冷却系統の点検が欠かせません。
これらは高電圧機器を扱うため専門知識を持つ整備士が対応する必要があり、点検精度が車検後の安心感に直結します。
走行距離が長い車やシビアコンディション(短距離走行や寒冷地使用など)では、予防整備をどの程度行うかが総額に大きく影響します。
以上を踏まえると、トヨタ車の車検費用は法定費用と基本料に加えて、使用環境と予防整備の範囲によって上下すると言えます。
ホンダ車の車検でかかる時間

ホンダは独自の技術を多数採用しており、その特徴が車検の所要時間にも影響します。
多くのディーラーや認定工場では、顧客ニーズに応えるために当日仕上げの枠を設けており、朝預けて夕方には引き渡しが可能な体制を整えています。
ただし、こうした短時間の対応を希望する場合、予約を早めに入れることが必要です。
ホンダ車の中には、CVT(無段変速機)やデュアルクラッチトランスミッション(DCT)など特殊な駆動方式を採用した車種があります。
これらの点検では油圧制御系統や電子制御ユニットの診断が不可欠であり、試運転や追加の確認作業が必要になる場合があります。
そのため、車検の所要時間が延びるケースがあるのです。
効率的に車検を進めるためには、事前のヒアリングが重要です。
店舗では受付時に走行距離や使用状況、直近で感じた不具合などを共有する「問診」が行われます。
ここで情報を正確に伝えることで、必要部品を前もって発注でき、当日の作業がスムーズになります。
特にホンダ車は純正部品の適合性が重視されるため、部品在庫の有無によって整備時間が左右されることも少なくありません。
したがって、ホンダ車の車検時間は、基本的には半日から1日程度を見込むと良いですが、特殊部品の点検や追加整備の有無によっては日数が延びる可能性もあると理解しておくことが大切です。
日産車の車検にかかる平均費用
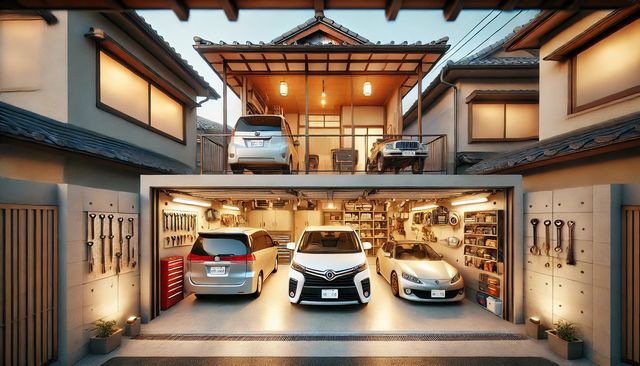
日産車の車検費用の基本構造は他メーカーと同様に、法定費用(自賠責保険料・重量税・検査手数料)と整備費用の合算です。
一般的な普通車の場合、総額で10万から15万円前後が目安とされます。
ただし、車種や年式、走行距離によって差が生じます。
特徴的なのは、電動化の比率が高い点です。
近年の日産はe-POWERやEV(リーフなど)の普及により、従来のエンジン車に比べて整備内容が異なるケースがあります。
特に12V補機バッテリーや回生ブレーキシステムの点検は必須であり、これらが追加費用の要因となることがあります。
また、ブレーキの摩耗具合や冷却系統の劣化は、使用環境次第で差が大きいため、早期点検が推奨されます。
見積もりを比較する際には、純正部品と優良部品(社外品)をどう使い分けるかが重要なポイントです。
純正部品は信頼性が高い一方で価格が高めであり、優良部品はコストを抑えやすい反面、品質差が存在します。
そのため、同条件での見積もり比較が不可欠です。
さらに、部品交換に伴う保証期間を確認しておくと安心です。
総じて日産車の車検費用は、ベースとなる法定費用に加え、電動化技術に伴う点検や追加整備の有無によって総額が変動するため、車種ごとの特徴を理解したうえで準備を進めることが大切です。
マツダ車の車検に必要な手続き

マツダは独自のSKYACTIV技術を幅広く展開しており、燃焼効率や排気制御において高い水準を実現しています。
この特徴は車検時の整備内容にも影響を及ぼします。
特にエンジンオイルや点火系統、排気系部品の管理は車両性能を維持するうえで欠かせない項目です。
SKYACTIV-G(ガソリン)とSKYACTIV-D(ディーゼル)では必要となる点検内容が異なり、ガソリン車は点火プラグや吸気系の点検、ディーゼル車はDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)の状態確認や排気センサーの清掃が求められることがあります。
特にディーゼル車では、短距離走行が多いとDPFに煤が堆積しやすく、車検時に清掃や交換が必要になるケースがあります。
逆に長距離走行主体のユーザーでは、エンジンの負荷が安定しているため不具合のリスクが低い傾向があるため、使用状況を整備士に伝えることで適切な判断を受けられます。
こうした車両特性を把握しておくことで、不要な整備費用を避けつつ、必要な整備を確実に行うことが可能となります。
なお、車検に必要な書類はトヨタやホンダと同じく、車検証、自賠責保険証明書、納税証明書、継続検査申請書、重量税納付書などが基本です。
これらはメーカーに依存せず共通の要件となるため、マツダ車だからといって特別な追加書類が必要になることはありません。
大切なのは、予約の段取りとともに、ディーラーや認証工場で車両の特性に合わせた点検を受けることです。
ダイハツ車の車検で知っておきたい点

ダイハツは軽自動車を主力とするメーカーであり、国内の軽自動車市場において非常に高いシェアを持っています。
軽自動車は法定費用が普通車に比べて低く設定されているため、車検総額も抑えやすい傾向にあります。
例えば2025年度時点での軽自動車の自賠責保険料は24か月で17,540円とされており、普通車よりも安価に設定されています。
一方で、街乗りを中心とする使われ方が多いため、低速域でのストップ&ゴーの頻度が高く、ブレーキパッドや足回り部品の摩耗が早く進むことがあります。
加えて、軽自動車は車体重量が軽い反面、エンジンや駆動系に負担がかかる傾向があるため、消耗品交換の頻度が普通車よりも多くなる場合もあります。
このため、早めに点検予約を入れ、劣化が進む前に部品を交換しておくことが安心につながります。
また、メーカー保証や延長保証の条件には、定期的な点検や整備記録簿の記載が必要とされる場合があります。
整備記録簿を紛失してしまうと保証の適用外となる可能性があるため、保管を徹底しておくことが推奨されます。
保証制度を活用できれば車検時の出費を減らせる可能性があるため、整備記録と保証制度をセットで管理しておくことが重要です。
スズキ車の車検の費用と特徴

スズキもダイハツと同様に軽自動車の割合が高く、ワゴンRやアルトといった車種が代表的です。
そのため法定費用が低く抑えられ、車検総額も比較的安価に済む例が多く見られます。
さらに、スズキは部品供給体制が整っているため、純正部品や社外部品の調達がスムーズであり、修理や交換にかかる待ち時間が短いのも特徴です。
一方で、近年のスズキ車にはスズキセーフティサポートと呼ばれる先進安全装備が搭載されている車種が増えています。
これには前方衝突警報や自動ブレーキ支援機能、車線逸脱警報などが含まれますが、車検時にバンパーやフロントガラス周辺の整備を行う際には、センサーやカメラの位置調整(エーミング作業)が必要になる場合があります。
エーミングには専用機器と技術が必要であり、費用や作業時間が追加されることがあるため、事前に確認しておくと安心です。
また、スズキ車は軽量化設計が進んでいることから燃費性能に優れる一方で、足回りの消耗やエンジンマウントの劣化が車検時に発見されるケースもあります。
総合的に見れば、スズキ車の車検は低コストで済む傾向にありますが、先進装備や消耗品の状態によって追加費用が発生する可能性を理解しておくことが必要です。
オートバックスやコバックで車検を受ける方法

カー用品店や車検専門チェーンを利用する方法は、ディーラー整備と比較して「短時間」「低価格」「立会い説明」といった特徴があります。
代表的な例として、オートバックスとコバックが挙げられます。
両者とも全国に多数の店舗を展開しており、予約のしやすさや料金体系の分かりやすさから多くのユーザーに利用されています。
オートバックスでは、最短60分から車検が可能とされる「短時間コース」が案内されることがあります。
ただし、この時間には受付や見積もり、会計などは含まれないため、実際には半日程度を見込んでおくと安心です。
オートバックスの特徴は、立会い形式で整備の必要性をその場で説明してもらえる点にあります。
部品交換の必要性や追加費用の有無を直接確認できるため、納得感を持ちながら車検を進められるのが強みです。
コバックは、45分から対応可能な「短時間車検」や、1日で完了する「スーパーテクノ車検」といった複数のメニューを展開しています。
短時間メニューは新しい車や走行距離の少ない車に適しており、基本的な整備点検を中心に行われます。
一方で、走行距離が長い車や追加整備が必要と想定される車両では、より時間をかけたメニューが選ばれることになります。
これらの店舗を利用する際の注意点として、予約枠や取り扱いコースが店舗ごとに異なることが挙げられます。
また、代車の有無、支払い方法、早期割引やキャンペーンの適用条件なども事前に確認しておくことが推奨されます。
特に、エーミング作業や特殊部品の整備に対応できるかは店舗によって異なるため、先進安全装備付きの車を所有している場合は事前確認が必須です。
店舗選びのチェックポイント
・当日仕上げの枠と受付締め切り
・代車や送迎、待合環境の充実度
・立会い点検の可否と説明の丁寧さ
・支払い方法と割引の条件
総じて、オートバックスやコバックといった大手チェーンを利用する方法は、スピードとコストのバランスを重視するユーザーに適しています。
ただし、細かな整備品質や特殊作業対応の可否は店舗ごとに差があるため、事前の情報収集と比較検討が欠かせません。
【まとめ】車検どれくらいかかるについて
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


